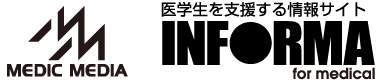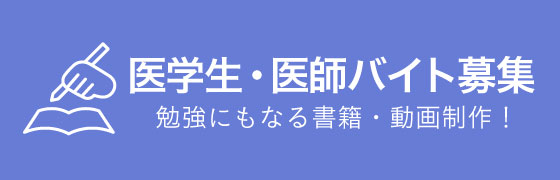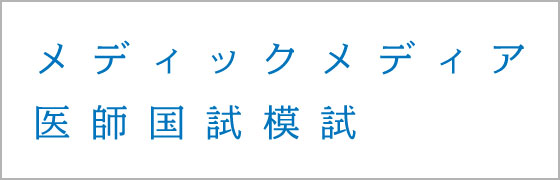第112回 医師国家試験【体験記】1人での国家試験対策
こんにちは,編集部のY.Tです.
今回は,1人勉強で国試対策を行った先輩の体験記をお届けします.
勉強環境で悩んでいる方や,
6年生になって環境が変わった方におすすめの内容です.
ぜひ,お読みください!
◆◆◆
第112回 医師国家試験【体験記】1人での国家試験対策
(T大学 T.Yさん)
◆◆◆
■□はじめに□■
みなさんの勉強スタイルは家派でしょうか?学校派でしょうか?
私は,家では勉強できないという”甘え”から,
5年生までは大学の図書館で勉強してきました.
しかし,6年次は諸般の事情で大学の近くから,
大学まで2時間かかる東京に引っ越して国家試験へ臨むことになったため,
基本的に1人で勉強することとなりました.
今回の内容は1人勉強をした体験記ですが,
6年次に勉強環境が変わった方にも読んでいただけたらと思います.
■□4〜11月は1人で勉強する方法を確立した!□■
私の大学の実習は6年の6月末までで,
7月以降は卒業試験と補講を除くと自学自習で国家試験対策を行う,
という仕組みになっています.
卒業試験が7月・8月・9月・11月の4回あり,
QBに掲載されている問題から出題されることになっていました.
ただし,内容が改変されているので丸暗記では解けないようになっています.
7月・8月・9月はQB全巻を1/3ずつ分けての出題,11月は全範囲が対象です.
以下は出題内容の詳細です.
7月:循環器,呼吸器,神経,小児科,公衆衛生
8月:血液,腎,泌尿器,代謝・内分泌,精神科,産婦人科,乳腺
9月:消化器・肝胆膵,膠原病,救急,整形,耳鼻科,眼科,皮膚科,麻酔科
まずは卒業試験対策として国試の全範囲を見ておこうと思い,
6年の4月・5月には実習時間の合間に既にメジャー科目の1周目問題を解き始めました.
通学中はスマホで,大学ではパソコンでQBオンラインを解き,
分からないことはレビューブック(以下,RB)で調べる,というスタイルを取りました.
続けて6月は7月の卒業試験の科目を解き,7月には8月の範囲を解き…という形で,
卒業試験のおかげではありますが9月初頭でQB全巻を1周,
11月初めには2周目も終えているという状態になりました.
CBTの時も問題演習量からのパターン認識で乗り切った私にとって,
1人でQBをひたすら解くという作業はさして苦ではありませんでした.
勉強拠点は週に1回程度行く大学,自宅,そして近所の図書館の3か所がありましたが,
タブレットさえあればQBオンラインで問題演習ができたので,
演習量に関しては1人でのハンデは感じませんでした.
ただ,荷物が重くなることから
本はRBやイヤーノート(以下,YN)程度しか持ち歩いておらず,
分からないことがあった際は納得するまで調べる,
という習慣が抜けてしまったのは今考えると響いたように思います.
友達に聞くという選択肢が使いにくい1人勉強ではなおさらです.
調べたり,会話の中で得た知識は忘れにくく,自信にもなります.
11月の卒業試験終了後は国家試験に向けて,次の3つのことを始めました.
①参考書をRBからYNに変える.
②苦手だった産婦人科を対策するためにmedu4を単科受講する.
③今まで見ていなかったMECのうちサマライズを見る.
卒業試験の勉強では,分からなかった項目にRBにマーカーを引いていたのですが,
CBTからRBを使っていたためもはやどれがどれか分からなくなるほど汚くなり,
5年で買ってから使っていなかったYNに切り替えました.
YNではQBを解いていて知らなかった知識に黄色,
模試や卒業試験で出題されたところに赤,
サマライズ等予想講座で強調されていたところにオレンジ,
という形で色をひきました.
②③のビデオ講座を見た後にもう一度QBを解きなおし,ついに3周目に達しました.
それが功を奏したのか年末年始の模試で成績がグンと上がり,
学内順位も全国順位もまず安心できるところまで到達しました.
■□1人勉強で成績がぐんぐん上昇!だけど…?□■
ただ,ここからの対策が良くなかったかなと,今考えると思います.
成績がかなり上がり,既にQBは3周を終えているという状況で,
1人勉強ということも相まって油断し始めてしまったのです.
もちろん勉強はしていましたが,他の受験生が必死に勉強量を増やしている時期に,
1日6〜7時間ほど,しかもダラダラと勉強するようになってしまいました.
また,最後の1か月は知識の抜けを見つける時期だと思っていましたが,
YNで過去にマーカーを引いたところを読む,
という対策しか取らなかったことも失敗でした.
人間の記憶はもろいもので,この時期は基本事項がぽっかり抜けてしまっていたりします.
(ましてや私は4月から既に勉強していたのも忘れやすさに拍車をかけたと思います.)
過去に間違えたところばかり見ていても,その忘却には気づけません.
加えて,問題演習をやりまくってパターン認識で解いていると,
この病気の治療法は知っているけど検査は知らないといった,
過去問に出ているか出ていないかでの知識のムラが際立ってきます.
グループ学習で友人と知識を確認しあうという作業があれば違ったのだろうか,
と国試が終わった今では思っています.
■□1人勉強を通して学んだこと□■
結局本番では,基本的事項が抜けて正答率の高い問題を落とし,
パターン認識にはまらない考えさせる問題に苦しみ,
(今年は特に患者ごとに考えさせるような問題が多かったように思います)
さらに元来の緊張しやすい性格とネガティブシンキングも重なって,
それまでの模試から一般臨床の成績が8%も落ちてしまうという惨敗を喫しました.
試験自体には合格できそうですが,今思うと1人で勉強するうえで,
特別に考えなければいけなかった部分があったなあと気づくことがたくさんあります.
1人勉強,というよりも6年次に勉強の環境を大きく変える場合には,
メンタル面も含めた本番までの想定をきちんと行って,決断することをお勧めします.
◆◆◆
いかがだったでしょうか.
勉強方法だけでなく,自分に合った環境や国試対策に有効な環境を見極めることも
重要なことだと感じました.
勉強環境に悩まれている方も,最近環境が変わった方も,
これを機に勉強スタイルを見直してみてもいいですね.
T.Yさん,貴重な体験記をありがとうございました!
(編集部Y.T)