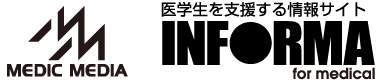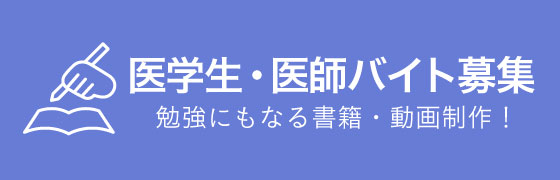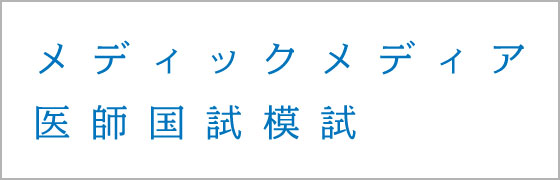[Dr.インタビュー] 和足孝之先生 「応援される力」で切り開くキャリア

臨床現場の第一線でご活躍されている先生にインタビューをする企画
第2弾は京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 准教授の和足 孝之先生です.
経歴
2009年、岡山大学医学部卒業.湘南鎌倉総合病院,東京城東病院,Mahidol University,島根大学医学部附属病院,Harvard Medical School,University of Michiganを経て,2024年より京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 准教授.
Dr.インタビュー
京都大学医学部附属病院 総合臨床教育・研修センター 和足 孝之先生
”和足孝之”ができるまで
編:最初に和足先生のお噂を耳にしたのは,「島根で医師のネットワークやコミュニティ作りに力を入れてご活動されている先生がいる」という話です.そこに至るまでの,先生のキャリアから伺えればと思います.
先生:元々,教育系に進みたいと思っていたんですよ.教育系の学部に2年,理学部に2年通いまして,大学の先生になろうと思っていました.それで,分子生理学の研究をやってるうちに,当時の先生が退官されるということがありました.その先生は元々医学部の教員をされていたんですね.
就職するか大学に残って研究するかを考えていたところ,その恩師の存在をきっかけに医学部への編入を考えるようになりました.当時お金が無かった私を当時の恩師があらゆる面でサポートしてくれたことで,医師になる道が開けたんですね.
当時は精神医学や免疫学に興味がありました.人の精神状態心理状態とミクロ・マクロレベルで身体機能とは結びついてて,例えば元気な人とか良く笑う人は,多くの場合ハッピーじゃないですか.ストレス耐性も強かったり.もっと言うと,身体的に筋トレばっかりしている人でdepression(うつ病)になっている方を見たことがありません.わかりやすく言うと、ニコニコしている人は元気でありやすく,病気になりにくいといえます.癌の予防などに,精神状況や持って生まれた性格的なものが関連しないか?今は医師のWellness(健康)などの研究をしていますが,当時はそういうことを調べたかったんですね.人生とは繋がっていると感じます.

徳田安春先生との出会い
編:岡山大学学士入学されて医学部の4年間を経て,その後,湘南鎌倉総合病院に5年勤務されていますね.
先生:湘南鎌倉総合病院は,当時から現在に至るまで,日本一の救急搬送件数を受けています.日本有数のその環境でレジデントをやり,研修医のリーダーをやり,チーフレジデントもやりました.卒後5年間では,朝も夜も土日もなく当時は診療を続けており,患者さんのために働くことに生きがいとやりがいを強く感じていました.それを経て,ガイラドラインやPubMedにもない臨床上の疑問がたくさん溢れて,アカデミックメディスンのようなことをやりたい,学問的にエビデンスや学術体系を構築したいと思うようになったのだと思います.湘南鎌倉総合病院の圧倒される環境で,臨床に飽和していた私にとって転機になったのは,メンターの徳田安春先生との出会いです.

徳田先生の素晴らしい点はメンターシップです.自分や組織のために人や若手を囲ったり,自分のために利用したり,働かせたり,というのが全くないんですよ.Mentorshipという学問があるのですが,本当のいいメンターの定義に全てあてはます.
徳田先生は,メンティーを自分を超えるプロフェッショナルとして育てるために,コーチングだったり,応援してあげたり(スポンサーシップ),誰かと誰かを紹介してあげたり(コネクターシップ)などを自然にされていました.古典的なメンターシップ,すなわち1対1で徒弟制度のように育てていく楽しみや重要性も,ここで知ったんですね.
教育への熱意
先生:患者を断らずに全て受け入れる,そんな湘南鎌倉総合病院の環境で鍛えられたあと,
徳田先生に,「臨床と教育と研究」をできるような人材になりなさい,と言われたんですね.そんな経緯で,東京城東病院に赴任します.そこで、「東京の病院で総合診療内科を作れ」と言われました.129床の小さな病院で,ハードトレーニングで確立した臨床スタイルがあったので,どんな患者さんが来ても楽しく診れたんですよね.勉強したことが役に立つので,内科を主軸した医師として働けることに感謝していました.
その後,タイのマヒドン大学熱帯医学大学に行きました.10何カ国の多様な国の医師等と,1年以上共に過ごしました.一緒に回診したり議論すれば,医者の実力って本当に大体分かるんですね.そこで,「自分が受けてきた日本の臨床教育はこんなにも国際的には実践できずに,ひどいのか・・」と思ったんですね.
ドイツ,イタリア,オーストリア,イギリスなどの国はなんとなくイメージしていたのですが,自分達の方が優れていると勘違いしていたタイ,フィリピン,インドネシア,バングラデシュ,インドなどの出身の先生たちの方が,しっかりとした臨床医学の力があって問診,診察といった当たり前のことを高いレベルで行っていました.
その国際感覚を初めて知って,度肝を抜かれて,日本はこのままではまずいと思いました.「日本に戻って教育に取り組まなければ」という情熱が出てきたんじゃないかなと思います.元々,教育系の学部に2年いましたので,教育が向いているところもやはりあるんでしょうね.
編:日本に戻ったきっかけは何だったのでしょうか.
先生:私がバンコクにいる時に,徳田先生に,東京の両国国技館の近くのちゃんこ鍋屋に呼び出されました.なんの話だろうと思ったら,バンコクから戻ったら島根大学に行くといいですよ,というお話でした.
島根大学は田舎だし,小さな大学であること,総合診療の需要が高く,ジェネラルメディスンのような教育をちゃんとできるし,医学教育改革をしやすいです,と.ぜひ行きなさい,と言われました.
最初,行ったこともない場所で怖いな・嫌だなと思いましたが,今思えば最高のメンターとしての役割を徳田先生は果たされていました.自分が尊敬しているメンターを純粋に信じてみたんですね.
行ってみると,当初は大学内で総合診療のプレゼンスはありませんでした.ドイツ実験基礎医学を輸入して保持してきた日本のシステムでは,英国や米国の臨床医学学派などと歴史的に親和性が乏しかった.一方で,診察の考え方や臨床推論や疫学的な考え方が重要であることは,みな分かっています.昨今では文部科学省や厚生労働省といった国の機関も,総合的な医師を養成しようとしています.少子高齢化社会となり,費用対効果が高く,質の高い医療を提供できる総合的な医師を増やす需要が高まっているからなのですね.
実際行ってみたら様々な困難もありましたが,まずはひたすら一人一人に会いに行って,お酒を飲んで,仲間にしていきました.一緒に働いたことがない医師に大学にきてもらったり,会議に出てもらったり,回診したり,ローテーションするなどして,ちょっとした違いの流派が違うと思い込んでいた医師達に交流を持たせました.総合診療の中で仲間を増やし,コミュニティを広げていった結果が,現在の「NEURAL GP network」に繋がっています.
編:「NEURAL GP network」とは,島根県発の総合診療医養成プロジェクトですね.地域の医療現場と大学を結ぶTeal型組織を構築することにより,過疎地や離島で働く総合診療医を繋げ,総合診療医養成の仕組みづくりがなされたと伺っています.
この取り組みの成果として,島根県には,他の地域よりもずっと多い総合診療医がいるんですよね.
先生:今,島根県内の総合診療専攻割合は約20%程度も増えてきていますし,5年連続で日本一になってきました.平均が2.6~3.3%ですから,ぶっちぎりに人気が出てきました.この島根モデルは今,色々な他県に輸出を開始しています.Learn and Shareの精神です.
応援される力、医師としての未来像
編:徳田先生をはじめ,メンターの先生との出会いなど,人との出会いが和足先生のキャリアに大きな影響を与えていると思います.医学生や研修医の皆さんに,大切にしてほしいことはありますか?
先生:レセプター(受け入れる姿勢)を持った状態の学生や研修医さんは,良いシグナルを出している先人達(人)と出会ってほしいと思います.数多くの学習者を見てきましたが,レセプターがない学生さんや研修医さんは,プロフェッショナルな職業としての成長は厳しいことが多いです.
そのためには,優れたメンターはいついかなる時も多忙であるので,できればメンターシップの中でも,コネクターとしての役割を提供できるメンターを探すことが大切です.もしくは,スポンサーシップをできるメンターを探すことです.
簡単に言うと,「君、それ興味あるの?僕ね,同期が実はこんなことをやってるから,あの先生に相談してみたら?」,これだけで十分です.コネクターシップですね.指導者として,教育者として,とても大切だと思います.
また,スポンサーシップとは,例えば「学会発表したいです」と.「あ、いいんじゃない.何したいの?」,「こういう研究やりたいんですけど」.その時に,相手の言ってることを聞いてあげて,それを否定せずに,どんどん若者の情熱や勇気に対して背中を押してあげるというのが,スポンサーシップなんですね.
往々にして伸びていったり,やっぱり良いな,と思った人は,良いなと思う指導者についていっているものです.良い先生と繋がることはとても大事です.
編:先生は,実際にメンターから受け取ったことを,後進に実践されているんですね.
先生:メンターとメンティー,後輩すら自分のメンターになり得ます.良い教育の連鎖は広げて次世代へ繋げていくことがとても大切だと考えています.
人から支えられる,人から教えられる,応援される力は重要です.「応援される力」に繋がるためには,人としての医師としての姿勢やモチベーション,志が大事だと思います.
研修医の皆さんも,各科を回る2ヶ月を有効に使うためには,将来の設計から逆算した時に,どんなことが必要かを考えながら研修をすると,無駄になりにくいですね.
編:その結果として,医師としての幸せがあるということですね.
先生:自分のウェルネス(総合的健康)というか,幸せに,健康に,医者として輝けるような場所を探しに行くのは大事なんじゃないかと思います.何を求めるか,どんな医師になりたいかを考えることが大切だと思います.働いた時の満足度,ウェルビーイングは,待遇や条件面だけではなく,他人からの感謝や,認められたときの喜び,仲間の存在によっても異なりますね.目に見える表面的なものではなく,本当に重要なものを見抜いてくことが,医師人生の幸福度を上げていきます.

総合診療の意義、教育の実践
編:最後に,これからのご活動の展望や,総合診療の大切さを改めて教えてください.
先生: 臨床との基礎医学の乖離を埋めるには,総合診療が大切です.総合診療は,横断的,俯瞰的な学問で,縦割り・臓器別・分子レベルの医学の視点では,理解されにくいです.しかし医療では,木を見て森を見ず,森を見て木を見ず,両方の視点が求められます.例として,High value care(質の高い医療),Diagnostic Excellence(診断の卓越性)など,一つの箇所だけずっと見ていてもわかりにくいのが,患者中心の現代の医療です.
以前,私は歴史的に評価されにくい我が国での総合診療の分野が,大学で評価されるために何が必要か調べました.大事なのは,臨床,教育,研究,リーダーシップ・マネジメントです.そこで,日本の総合診療を研究で押し上げたいと思いました.総合診療の仲間達が評価されるために,大学の中で一番研究業績も上げようと思い,島根大学の中で病院長賞や最多英語論文といった賞を頂くに至ります.
もう一個は教育の面です.なぜかと言うと,患者さんは分かりやすく「この疾患です!」と訴えてくる訳ではありません.患者さんが訴えるあらゆる主訴から,本来は全ての疾患を想定して鑑別を出来なければなりません.これは,横断的診療科である総合診療の分野で教えるのが,臨床医を育成するにはおそらく最も向いていることが国内外の研究でわかってきています.
またそのように貢献すれば,学生や研修医は,良い教育であると感じ取ってくれると確信してきました.給料が安くても,田舎でも,良い教育があれば若い人は集まります.大学教員が無理に教えるよりも,実際に地域の臨床現場で働いてる本当のリーダーが大学で教える方が,医学生にはめちゃくちゃ受けるんですよね.
臨床,教育,研究とリーダーシップ・マネジメントが機能することで,島根は輝いてきていると思います.
自分のメンターのメンターである黒川清先生から,「優れた教育を受けた人しか,優れた教育者になれないことが多い.だから,良い教育を受けた者は、良い教育を与える権利がある.そしてそれは義務なんだ」,と言われました.今後も良い教育を,現在の所属先である京都で実践していきたいですね.

編:本日はありがとうございました.