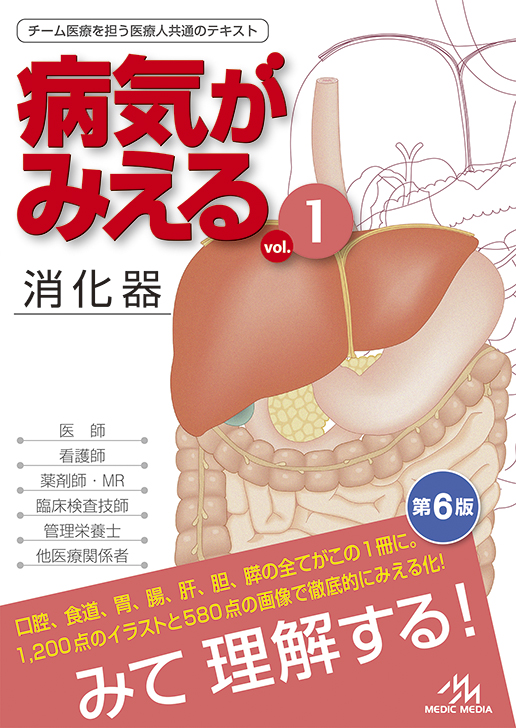
病気がみえるシリーズ
新シリーズ「病みえストーリーズ」始動!
皆さんは,教科書には載っていない,患者さんの体験を想像できていますか?
普段,手に取る教科書や参考書では「症状」や「経過」「治療」などが無機質な知識として並んでいるように見えるかもしれません.しかし,その裏側には,患者さんやその家族が抱える不安,生活の変化,そして葛藤があるのです.「病みえストーリーズ」シリーズでは,そうした患者さんや家族の体験をストーリーを通じて描き出します.
教科書では端的に記されている症状が,日常にどのように影響を及ぼし,患者さんがそれをどう受け止め,生活を再構築していくのか…….そのプロセスを追体験することは,将来、皆さんが患者さんの言葉に耳を傾ける際の糧となるはずです!
今回は,「ギラン・バレー症候群」を発症した水泳選手のストーリーをお届けします.この疾患が患者さんや家族にどのような体験をもたらすのか,ストーリーを通して学んでいきましょう!
作者:奈々崎 優
監修:戸島 麻耶(京都大学医学部附属病院 脳神経内科)
水泳,200m自由形.ついこの間まで表彰台常連だった山口はその日,水に溺れるという屈辱を味わった.
***
「おう,久しぶりじゃん」
天井の開いた屋内プールには夏の日差しが差し込んでいる.それでいて水泳競技に邪魔な風は極力排除されているプロ仕様の練習場だ.
練習前の準備運動をするべくプールサイドにいた洋一は後ろから声をかけられた.
「ちょっと体調崩してな.練習期間が空いてしまったよ」
「風邪か? 最近流行ってるもんな」
「結局何だったかは分からないけど,大変だったよ.38℃,39℃ぐらいは出てたしな」
「うわー,お大事に.ってもう遅いか.今日はゆっくりやれよ」
そう話しかけるのは同じく日本代表経験のある加藤太郎だ.家族以外にほとんど深い知り合いのいない洋一にとって珍しく気の置けない親友である.
「分かってるって.だからこんな時間かけてストレッチしてるんだろ」
実際,練習場の開場時間の8時から山口はそこにいた.そこから10時の今まで準備運動をするとは洋一自身も想定していなかった.
しかし,どうにも体の違和感が抜けない.
両足の先からふくらはぎにかけて,自分の足が自分ではないかのような不思議な感覚.
それは病み上がりのせいだろうと何度も自分に言い聞かせたが,嫌な予感が洋一を闇に引きずり込んで離さなかった.
「なにしてんだ.そろそろ泳ごうぜ」
すぐに水に入ってしまった加藤に遠くから呼びかけられる.加藤は準備運動はゆっくりと水の中でするタイプだった.
「ああ」
しがみついては離さない,一抹の不安を払って洋一は入水する.
(なんだ,いつもと同じじゃないか)
水に入ってみれば却って安心感を覚える.0歳のころから水泳をしていて今や28年も水の中にいる洋一にとって水中の方が居心地がよかった.
よし,泳いでみよう.
山口洋一の練習での練習初めの一週目は本気で泳ぐのがルーティンだ.そのためにプールサイドでの準備体操を入念にやるのだ.
全身の力を使って壁を蹴る.美しいストリームラインによって全く減速せず5m,10mと進んでいく.
しかし,いつもより距離が短い.呼吸も苦しい.息継ぎが必要だった.
「ぷはぁ」
足の不調は全身に影響し,息継ぎも上手くできず,口の中に水が流れ込む.
これは,泳速をできる限り落とさないため水面ラインギリギリで息継ぎをしたことに起因する.そして洋一は自分の体調を気にせずいつもの感覚で息継ぎをしているからだった.
負けず嫌いでもある洋一は不調であればあるほど今までの練習通りに泳ごうとする.
苦しい.泳げば泳ぐほど自分が深くに落ちていく感覚.洋一の長い水泳人生で初めてだった.
いつしか,顔を水面より高く上げることもできず泳ごうとしていた.
「おい!」
異変に気付いた加藤が駆け寄り洋一の肩を担いだ.
「大丈夫か」
すくい上げられプールサイドに座らせられる.
「すまん,ちょっと無理してしまったらしい」
「気をつけろよ.俺たちが水難事故なんてシャレにならないぞ」
「分かってる」
無理して泳ごうとしたあまりに大量の水を飲み,気管にも入ってしまっていた.
並外れた心肺機能によって意識が遠くなることはなかった洋一だったが,こうなってしまうと,体の違和感は本当の不調だったと認めざるを得なかった.
それでも,山口の目には闘志がみなぎっていた.
大会は来週に迫っていた.
***
「パパ!」
玄関の重い扉を開けると奥の居間から廊下をタッタと駆けてくる.
「ただいま~.真理,いい子にしてたか?」
真理は助走をつけて勢いよく洋一の胸に飛び込んでくる.洋一はそれを両腕で持ち上げ,抱きかかえる.いつもならなんともない親子の触れ合いだったが,今日に限っては受け止めきれず少しのけぞってしまった.
「いて」
背中に玄関のドアノブが突き刺さり少しだけ声を上げる.
「パパ,大丈夫?」
それを見て真理はしゅんとしてしまっていた.
「平気だ平気.な.ご飯食べようか.ママが美味しいの作ってるよ」
洋一は痛みに耐え,鼻腔をくすぐる匂いのする居間へと注意を仕向けた.
真理は自分のせいで人を傷つけたと思ったかもしれない.でも娘にそんな悲しい顔はさせたくない.
真理に笑って幸せに育ってほしかった.真理が生まれてからというもの,洋一が水泳を続ける理由のほとんどはそのためだった.
***
「いただきます」
寒色の光に包まれ家族三人揃う.見る人が見ればミニマリストの一家だと思われるかもしれないほど居間には物が少なく,その代わりに丁寧に配置されたホワイト系の家具はモダンなリビングを表現していた.
というのも洋一の妻,美恵はインテリアデザイナーを営んでおり,居住空間の配置については造詣が深かった.ただ,家事育児の隙間を縫っての仕事であり,家計の収入減のほとんどは洋一に依存していた.
「どう? 調子は.来週,あるんでしょ」
食事も進むと洋一の仕事の話になる.洋一としてはあまり話したいところではなかった.
「まあまあかな.加藤達も出るみたいだし,優勝できるかは分からないけど」
「あら,自信がなさそうなの珍しいね.調子よくないの?」
「まさか.やれるだけやるよ」
インターハイの表彰台で告白してから今まで連れ添っている美恵はさすがに洋一の挙動不審に勘付いていた.
しかし,この時は指摘するほどではないと感じていた.夫が稼ぎ,妻が家で迎え入れそれを支える.そうしてここまでやってきていた.それに洋一の不調がまさか,練習で溺れるほどだとは思ってもいなかった.
「おかわり!」
団らんは続く.
洋一は箸を持つ手にすら違和感を持つようになっていた.
***
食事を終えても洋一は立ち上がれずにいた.家事を手伝うこともなく,じっと座っていた.
朝の練習の時よりも症状が少し酷くなっている気がする.
洋一がまず初めに感じたのは,歩きにくさだった.最初はケガかと思った.ただ,片足ではなく両足に違和感があるのはおかしい.
では病み上がりの筋力低下だろうか.それにしたって歩きにくさやふらつきを感じる要因にはならないような気がするし,この自分自身の足として動かせない感覚は妙だ.
そういえばいつからか足がしびれるような感覚もある.
「ごめん,もう寝るよ」
「そう? 久しぶりの練習疲れた?」
「ああ,ごめん」
壁を伝いながら寝室へと向かう.
洋一もはっきり言ってこの症状が異常なことは分かっていた.このまま徐々に症状が進行して全身が動かなくなるかもしれない.
考えた瞬間,恐怖で鳥肌が立つ.そうやって徐々に体が動かなくなり,意識だけ清明なまま人生を全うする病気があることをうっすらと知っていた.
病院に行った方がいいのだろうか.
いや,いい.大会も近いんだ.大事な大会だ.病み上がりから調子をフルに戻すために練習の日程が詰まっている.一日たりとも予定を崩すわけにはいかない.
この症状も気のせいだろう.明日になったらよくなっているはずだ.
実のところ,洋一は無意識で病院に行くことを拒絶していた.ようやく回りだした家族計画.人生設計を崩しかねない大病を想像すると,恐怖で怖気づいてしまった.病院に行くと病気が確定してしまうという忌避感もあったのかもしれない.
早く眠りに付こうと気分にそぐわぬアロマを焚いて無理やり暗くした寝室で横になる.
目を閉じると真理の顔が浮かぶ.
今が踏ん張りどころだと,そう思った.
***
「Take your marks」
洋一は何よりもこの瞬間が好きだった.
「ピィ!」
選手たちが一斉にキックスタートする.闘いが始まる前の一瞬.ライバルたちの間にはある種の一体感のようなものがある.ピンと張りつめた緊張は観客にまで伝播する.そのプレッシャーが堪らなかった.
多くの観客が入った日本選手権の会場は熱気に包まれていた.この大会では世界選手権やオリンピックの選考も兼ねており選手たちの気も引き締まっている.
Aブロックの選手たちが競技を終える.Cブロックの山口は準備を始める頃合いだ.しかしいつまでたっても洋一は控室から出てこなかった.
「はぁはぁはぁ」
塩素の臭いのする控室を出た廊下から観客の待つプールまでは10段ほどの階段が敷かれていた.
たった10段.それすらも洋一にとっては鉄壁のように道をふさいでいた.
「おいおい,大丈夫か」
一段一段,丁寧に,滑り落ちないようにゆっくりと登る.
今では両足に力がほとんど入らない.足の先から始まった違和感は今や障害に発展し,這い上がってくるかのように上へ上へと全身を侵していた.
横からは泳ぎ終わった友の声が聞こえる.だが答えているほどの余裕がない.
意識も朦朧としながらスタート台に立つ.そこに着くまでに体力を使い果たしていた.自分の番かも分かっていなかった.ああ,Bブロックはいつ終わったんだろう.
洋一の頭は恐怖と焦燥に焼かれていた.
スタートのために足元を見る.足の裏から鮮血が流れていた.
来るまでに何か踏んだのだろう.洋一は気付かなかった.少し前から両足の感覚はなくなっていたからだ.
自殺行為だ.そう思う自分がいる.
訳の分からない病気にやられ,満足に体が動かせない状態になった俺に何ができる.いかに大事な大会だといっても勝つどころか他に迷惑をかけるだけだ.
それとは別に根拠のない漠然とした自信を持っている自分もいた.
スイマーとして人生をかけてきた洋一にとって水の中こそがホームグラウンドだった.プールでは無敵だったのだ.
スタートを切ってしまえばきっと大丈夫だ.そう思おうとしていた.
なぜなら,此処こそが,最後の舞台だと直感していたから.
スタートの合図が始まる.
真理.見ていてくれ.お父さんがかっこいいところを見せるから.
そう奮い立たせる.そんな決意とは裏腹に真理が会場に来ていないことを願っていた.
電子音が鳴る.
洋一は完璧なタイミングでスタートを切る.体が動かなくたって,思考は冴えていた.どうやら脳を侵すような病気ではないようだ.
全力で水を切る.しかし,思ったほど進んでいない.周りから置いていかれているのも感覚で分かる.
瞬間,理解する.入水さえすれば,などというのは身勝手で空虚な理想でしかないことに.
それでもできるだけ進む.
体が痛い.動かない.息継ぎも碌にできない.肺が千切れんばかりに悲鳴を上げる.
もはや勝負にはなっていないのは分かっていた.水から上がればどんな声が聞こえるだろう.悲鳴だろうか.ブーイングだろうか.嘲笑だろうか.
突然,緊張の糸が切れた.泳ぐことをやめ,ぷかぷか浮かぶ.
会場の真ん中で救助を待ちながら,洋一は打ち付ける波の中で気付かれないように少し泣いた.