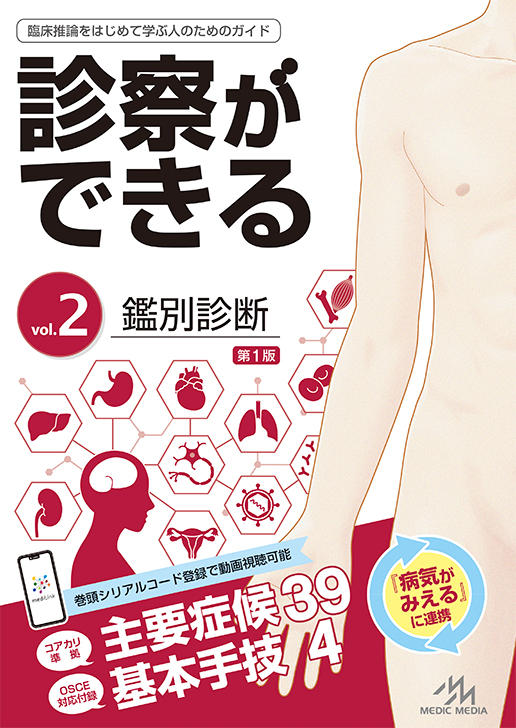
診察ができる vol.2 鑑別診断

臨床現場の第一線でご活躍されている先生にインタビューをする企画
第一弾は諏訪中央病院 総合内科の山中 克郎先生です.
経歴
1985年,名古屋大学医学部卒業.名古屋掖済会病院,名古屋大学病院 免疫内科,バージニア・メイソン研究所,名城病院,名古屋医療センター,カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF),藤田保健衛生大学(現在の藤田医科大学) 救急総合内科 教授 / 救命救急センター 副センター長,諏訪中央病院 総合診療科 院長補佐,2019年-2024年福島県立医科大学 会津医療センター 総合内科 教授を経て2024年諏訪中央病院 総合診療科
諏訪中央病院 山中 克郎先生
メディックメディア編集者(以下編):まず初めに,先生は,藤田医科大学救急総合内科の教授として病棟総合診療,救急医療,外来診療で活躍されたあと,地域医療はまだ経験されていないという思いで教授を早期退職し,諏訪中央病院に転勤されました.その後,会津医療センターで総合内科学の教授になられ,今年定年退官され,再び諏訪中央病院に戻られました.現在,どのように臨床活動をされているのか,お話を聞かせいただければと思います.
山中先生:諏訪中央病院に5年ぶりに戻りました.5年前と変わったと思うことがあります.救急室や外来を受診する高齢者がすごく増えました.

編:先生は今,臨床現場ではどのような形で働かれているのですか.
山中先生::救急室にウォークインで来院される方の外来診療を研修医と一緒に行っています.まず研修医が30分ぐらいで問診と身体所見を取り,私に相談に来ます.その後,一緒に診察をして診断に必要な検査を行い治療します.訪問診療にも出かけています.高齢者が多くなっているので,訪問診療のニーズも以前に比べるとかなり高くなっています.
他に,人間ドックや外来診療もやっています.諏訪中央病院で週に3日働き,それ以外は名古屋や福島で若手医師教育や診療応援を行っています.
編:退官された後,もう一度一臨床医として現場にあり続けるというのは,ずっと前から考えられていたことだったのでしょうか.
山中先生:管理職よりも一臨床医として最前線で患者さんの診療をし,若手医師教育をしたいと思っていました.
編:今後の臨床活動のなかで,どういうことを重視したいですか?
山中先生:これからAI(人工知能)がどんどん医療現場に進出してくると思います.迅速な診断や治療ができ良いこともありますが,弊害も起きます.AIを全面的に信頼することはできません.人間にしかできない医療が必ずあります.

編:具体的にはどういうものですか?
山中先生:まず患者さんの訴えに共感して,「それは大変だったですね」「辛かったと思います」「今日来ていただいて本当によかったです」と声かけをします.そして昔ながらのドクターがやっていたように,患者さんの背中に優しく手を添えて,胸に聴診器を当て心臓の雑音や肺の呼吸音を聞き,お腹を丁寧に触って痛いところを確かめたりします.それはAIにはできないことです.
私は医師としてのキャリアの終盤に差し掛かりました.正確な診断を得るため,問診の技術をもっと磨きたいです.そして丁寧な診察で患者さんに寄り添うことを若手医師や医学生に教えたいです.
編:頭で診断をすることだけでなく心で寄り添うことも重要なのですね.研修・教育についてもお伺いしたいのですが,普段教育指導されるのは,主に研修医の方なのですか.
山中先生::一番多いのはやはり初期研修医です.救急外来で診療の指導を行います.講演会では自分が経験した教育的な症例を提示し,医学生や研修医の皆さんにどのような問診や診察をすれば診断に結びつくのかを考えてもらっています.心臓の聴診の仕方やめまいに対する診療を模擬患者さんに協力してもらいながら実演します.
編:救急外来などの初期研修医の方が最初に診察されるというお話がありましたが,限られた時間で初めて会う患者さんと信頼関係を築いていくという点について意識されていることはございますか.
山中先生:最初の1分間で患者さんの心を掴むことをすごく重視しています.そのためには笑顔と誠実さ,知性が大切です.どんなに優しく振る舞っても,「できる医師」だなと感じてもらえないと患者さんに信頼してもらえません.例えば「この薬を飲めば咳は1週間ぐらいで良くなりますよ」と回復の見込みを説明することが大切です.研修医と一緒に診察しながら,それを実践してみせ,そこから学んでもらおうと意識しています.

編:山中先生の実際の診察を直接みて学べるのですね.
山中先生:はい.ドクターは他人の診察を見る機会があまりないのです.
もちろん私が診断を間違えることはたくさんあります.私がどうして間違えたかを研修医に見てもらうのもすごくいい教育になると思っています.「診断を間違えちゃったね.この症状に引きずられちゃった」と誤診の原因を説明しています.
私自身もいままで臨床能力が優れた医師の診察をたくさん見せていただいたのです.それがとても役に立っています.
編:診察をしたあと,研修医は先生とディスカッションし臨床推論の過程などを教えてもらうということもあるのですか?
山中先生:その通りです.そういうことを繰り返しやっています.
編:最初の1分間での信頼関係が大切っておっしゃっていただいたのですけど,どうしても当直の時など,あまり患者さんへの対応に十分時間をとることができず少し信頼関係を損ねた状態で診察が始まってしまうみたいな場面が若手医師の頃にはあると思います.そういった不信感を抱いてしまったような患者さんを対応する必要がある時の研修医の方へのアドバイスなどはございますか.
山中先生:救急室では患者さんの体調が悪いし医療従事者も忙しい.どうしても緊迫した関係になりがちです.しかし,そういう時だからこそ,患者さんと家族を思いやる気持ちを持たないといけないと思います.「どうして,これくらいの症状で救急車を呼んだのですか?」「なんで午前中に外来を受診しなかったのですか」と問い詰めたり,「39℃の熱なんて子供ならよくありますよ」と発言したりすることはよくないです.そうではなくて,「夜間に熱が出たら心配になっちゃいますよね. 私も自分の子供が39℃の熱を出した時,白血病になったのかとすごく心配でした」という共感的なコミュニケーションがトラブルを防ぐために重要です.
編:限られた時間でも,相手の気持ちを思いやることが本当に大切ですね.
山中先生:それは本当に大事だと思っています. 最近は患者さんのプライバシーを守るため,「321番の方~2番診察室にお入りください」とマイクで受付番号をアナウンスします.しかし,私はこれが苦手です.必ず診察室のドアを開けて顔を出して「321番の方お入りください」と言うようにしています.待合室にいる患者さんの様子を細かく観察することが大切です.前の椅子に手をかけながら立ち上がったら下肢の筋力が低下していると推測できますし,立ち上がった途端にふらついたら,バランスが悪くて転倒のリスク大きいとわかります.
次に患者さんが診察室に入ってくるまでの歩き方を見ます.例えば,両足の幅を広げガニ股で歩いてきたら(開脚歩行),小脳失調か後索障害です.
歩行の途中から「おはようございます.今日担当する山中です」と話しかけることができます.一人で来ているのか家族と一緒なのかも分かります.そんな詳細な観察を行うことが臨床医には必要だと思います.
編:患者さんの心を掴むっていうことを意識されている時にでも,同時に冷静に観察して情報を集めているのですね.
山中先生:そうなのです.以前,神経内科医に「僕たち色々診察はするけど,歩行の診察は最も情報がある」と言われたことはずっと覚えています.
編:山中先生は,心を掴んだあとは「攻める問診」が重要と繰り返しお話されています.初めての読者の方に向けて,お教えいただけますでしょうか.

山中先生:3分間はなるべく口を挟まずに患者さんの訴えをよく聞くようにしています.「そうですか」「それは大変でしたね」という共感の言葉は述べるのですが,自分からはそれ以上の質問はせず,患者さんには困っていることを話してもらいます.
しかし,その3分間も,ただ話をぼーっと聞いているだけではなくて,この人の病気は何だろうと妄想しながら聞いています.この時はたいてい2つぐらいの鑑別疾患を思い浮かべていて,この頭痛は片頭痛かな,くも膜下出血の可能性もあるかも・・と考えながら患者さんの話を聞きます.
編:はじめはOpen Questionで傾聴するのですね.
山中先生:はい.3分ぐらいの話の後は,いわゆるノイズと言われるような,診断とは無関係の話が続いたり,同じ話の繰り返しになったりすることが多いのです.研修医や医学生には「3分経ったら,患者さんの話は聞くな」と教えています.そのあとは自分が考えた鑑別診断が正しいかどうかを確認する大切な時間なのです.例えば片頭痛患者さんだったらいくつかの特徴的な症状,「電灯を見た時に眩しくないですか」「頭痛ひどくなると吐き気がしませんか」「頭痛がひどくなると寝込んじゃいませんか」と質問します.患者さんの話を聞いているだけでは,絶対に診断はできないのです.その疾患に典型的な症状をどんどん質問していく技術が必要です.私はこれを「攻める問診」と呼んでいます.
編:Closed Questionで確認していくのですね.鑑別が2,3個頭に浮かんでいらっしゃる時っていうのは,片頭痛の質問セットと,他の鑑別疾患の質問セットは順に聞いていくのですか?混ぜながら聞いていくのですか?あとこれは違うなと思ったら次のセットに行くようにされているのですか?
山中先生:最初は致死的な病気を除外しないといけません. 頭痛のred flags(危険信号)というものがあって,それに当てはまる頭痛の場合は致死的な疾患であることが多いので最初に確認します.例えば,50歳以上で初めて起きた頭痛や,雷鳴様頭痛という1分ぐらいで最高の痛みとなる頭痛です.いつもの頭痛とはぜんぜん違う,経験したことのないようなタイプの頭痛,意識障害や上肢の麻痺のような神経障害を伴ったものも危険な頭痛です.
まずred flagsに当てはまるかどうかをチェックし,大丈夫なら,頻度が高く今回の症状にあてはまりそうな疾患に対して,それぞれの疾患に特徴的な症状を確認し鑑別診断を絞り込んでいきます.
編:致死的となるものを除外してから,一番可能性が高いと思った鑑別疾患を想起し問診していくのですね.
山中先生:そのとおりです.頭痛の場合は二次性の頭痛をルールアウトすることがまず一番大切だと思います.
編:現在の諏訪中央病院での救急外来では大体1日あたり何人ぐらいの患者さんを研修医の先生と診察されるのですか.
山中先生:救急外来の指導は半日です.2名の研修医の指導をすることが多いです.研修医1名あたり,2−3名の患者さんを担当してもらいます.研修医が最初に問診と身体所見を取り,私にプレゼンをします.その後,一緒に診察しながら鑑別診断を絞り込んでいきます.
編:当直の時以外は自分で外来を担当することはほとんどないという研修医の人が多いと思いますが,諏訪中央の場合は日中の救急外来でも研修医が担当できるのですか.
山中先生:そうです.私は実践教育がすごく大事だと思っています.いくつかの大学から研修医が学びに来てくれます.彼らは「こんな研修はなかった.勉強になります」と言ってくれます.
以前,大学で教えていて感じたことがあります.学生は4年生から5年生,5年生から6年生になるにつれ,確かに医学知識は増えますが「臨床ができるな」と思ったことは一度もないのです.ところが, 6年生が研修医になると,すごい勢いで臨床能力が向上していきます.やはりOJT(On the Job Training)は大変重要です.
編:こういうことを意識している研修医は伸びるなという特徴はありますか.
山中先生:やはり仕事熱心な人です.一つ一つの症例を大切にしてそこから多くを学び取ろうとする研修医は実力がつきます.いきいきと楽しく仕事をしています.
編:救急外来は基本的に諏訪中央病院の研修医の先生は全員救急外来を必修で回るのですか.
山中先生:ある期間は朝から夕方まで救急室で勤務します.救急のローテーションでないときは曜日を決めて,救急外来の診療に入っています.
編:訪問診療についてはどういったことをされているのですか.
山中先生:車で10分くらい離れた場所にリバーサイドクリニックという病院の診療所があります.訪問診療はそこから出発します.看護師さんと私で患者さんのお宅に伺います.利用者は高齢者が圧倒的に多く,心不全やCOPD,脳梗塞後遺症があり寝たきりのため通院ができない方です.外来担当医が私達に患者さんを紹介してくれます.
編:外来から在宅に移行した方の経過をみていくのですね.ここまで救急外来と訪問診療のお話をお伺いしました.今まで山中先生が色々な経験をされてきたと思うのですが,これから総合診療医を目指される研修医の方はどのような仕事を目指していけばよいと思いますか.
山中先生:総合診療医は,その地域や病院のニーズによってどんな仕事もやらないといけないと思うのです.
例えば,地域に行けば,診療所がメインの職場になるでしょうし, 都会なら,総合病院で入院患者さんを診療したり,救急や集中治療をやる医師もいます.いろいろな仕事がありますが,まず外来診療が重要です.各診療科の外来はありますが,高齢者はたいてい複数の疾患があり,どの科が中心になって診ればよいのかわからないときがあります.そういう複合疾患がある患者さんは,総合診療医が主治医になって診療するのがよいと思います.
救急のニーズはとても大きいです.助けられる病気,例えば敗血症では正しい治療をすれば元気になります.また集中治療による救命もすごく大事です.
診療所をベースに家庭医療を行い,家族全員の健康を管理し,社会背景を考えて必要最小限の投薬や病気の予防に力を注ぐという仕事もあります.
編:一言で総合診療医といっても様々な仕事のパターンがあるのですね.

山中先生:一般外来,入院診療,救急医療,集中治療,家庭医療の分野があります.
この5つの柱があり,どこに軸足を置いてやるかは自由に選ぶことができます.興味があるところに行けばいいと思いますが,最初から一つの分野に集中しまうと,そのことしかわからなくなってしまいます.若いうちはなるべくこの5つの柱を幅広く学んで経験を積んだ方がいいと思っています.
編:総合診療医って言うと難しい診断を当てるプロのようなイメージもあると思うのですけど,それは一側面で,この5つの要素を担っているわけですね.
山中先生:そうです.診断も大事ですが,それだけが重要ではないです.
編:今,先生は総合診療医として,その中でも特に救急と一般外来,訪問診療という形で臨床を継続されているのですね.
山中先生:はい,そうです.私がこれをやりたいと言ってやっているわけじゃなくて,ここの病院にそれが必要だったのです.リタイアしてからは,若い医療従事者や地域の方を助けたいと思っていました.最近は男性も育児休暇を取得しますし,体調が急に悪くなったり,女性の場合は妊娠しある期間は働けなくなることもあるので,どんな仕事もやるようにしています.
編:諏訪中央病院にまた戻りたいって思ったこの病院の良さは何ですか.
山中先生:諏訪中央病院は若い医師がたくさん集まる病院で,しかもすごく勉強熱心な人が多いのです.優秀な指導医も数多くいます. 若手医師から刺激を受けることによりベテラン医師も自分をさらに高めることができます.そして,私は地域が大好きです.人々は生活の便利な都会に集まりますが,誰かが地域をみてあげないといけない.地域医療を行っていた会津で定年となった後も,どこかでまた地域医療に貢献したいと思いました.長野の自然環境が好きです.綺麗な山々に囲まれ,夏も涼しく,野菜が最高に美味しいです.
編:地域医療というお話が出ましたが,一臨床医としての先生の活動も素晴らしいと思うのですが, 奥会津の地域医療をテーマにプロジェクトの立ち上げから関わり推進されていらっしゃったという業績もすごく大きいことだなと思います.どういった経緯で,どういう企画を立ち上げられて,どう推進されたのか,経験をお教えいただけますか.
山中先生:55歳の時に藤田医科大学を早期退職し諏訪中央病院に赴任しました.地域医療を勉強しながら,もう一度内科を学び直そうと思ったのです.
名誉院長の鎌田實先生から地域医療の原点を学び,臨床能力が抜群に高い佐藤泰吾先生(現院長)からたくさんのことを教えてもらいました.諏訪における5年間の生活で若手医師との交流もでき,地域のことが少しわかってきたなと思った時に,古くからの友人である福島県立医科大学総合内科教授の濱口杉大先生から連絡がありました.福島県には,太平洋側から順に,浜通り,中通り,会津の三つのエリアがあります.「東日本大震災後,浜通りと中通りは復興が進み,医局員の派遣もできるようになりましたが,会津は全くの手つかずなんです.会津には福島県立医科大学のサテライト病院である会津医療センターがあるのですが,総合内科の教授が退官されることになり後任をさがしています.来ていただけませんか」と.
妻と相談しますから数日間考えさせてくださいとお伝えしました.最初は断ろうと思ったのですが,妻が福島は震災で本当に大変な状況になったので,福島県に少しでも貢献できるなら素敵ねと言ってくれたのです.僕自身も震災から数日後,気仙沼(宮城県)に入り医療活動をしましたが,1週間の滞在だけでした.福島のために役立つことがあればしたいと会津に行く決意をしました.
編:そして5年間会津で臨床をされていたのですね.最初はどのようにプロジェクトに関わったのですか?
山中先生:大学からは医局員を増やして, いろんな診療所に人を派遣して欲しいと言われました.診療所がある場所は会津若松市から車で40分くらい離れた奥会津と呼ばれる山間部です.でも,若手医師を診療所に派遣すれば,医学教育の機会が減ります.積雪が2-3メートルになる場所なので家族の生活も心配です.何か良い方法はないだろうかと考えながら,奥会津の医療機関を回りました.その時にふと思いついたのは,訪問診療のチームを作って,そのメンバーが移動しながら地域全体を回ろうというアイデアです.
編:発想を逆転させたのですね.
山中先生:一台の車に地元で採用した運転手,看護師,医師が1人ずつ乗り地域を巡回し訪問診療を行う.このチームを2つ作れば,奥会津全体をカバーすることができると思いました.この構想を紙面にまとめて会津医療センターの院長に報告しました.
福島県も会津の過疎地域での医療をどうするか大変困っていたようで,特別予算をつけるのでやってみてくださいということになりました.
編:予算がついたのですね.
山中先生:はい.その予算がついたので,鎌田一宏先生はじめナースの方々,ドライバーや事務をリクルートすることができました.素晴らしいチームができて,奥会津を拠点に訪問診療と訪問看護を展開できました.運が良かっただけですが,自分の夢を描いて,それをいろんな人にプレゼンすると夢が叶うことがあります.若い皆さんもどうすれば社会貢献になるのかを考えていただき,上司に熱弁を振るって具体的に説明することが大切です.
編:スタートを切れたあとはどうだったのですか?
山中先生:新しいプロジェクトではチームワークがとても大切です.リーダーの鎌田先生は人に好かれるキャラクターで,うまくチームをまとめてくれたことが大変良かったです.最初の半年ぐらいは数人の利用者しかいなかったのですが,その後はどんどん口コミで利用者が増えていき,今では約110名の患者さんを24時間365日体制で見守っています.看護師さんの優しい振る舞いのおかげで,地元の方々に大変喜んでいただいています.
編:鎌田一宏先生は山中先生と一緒に「問診☆攻めNIGHT」(mediLink動画で視聴できるラジオ形式の臨床推論動画)で私達もお世話になりましたが,周りを明るくできるお人柄で,番組でもそれが実感できましたね.ところで,訪問診療のチームが移動して地域全体をカバーする体制今まで日本にはあまりなかったのですか.
山中先生:都道府県が主体になってやる訪問診療はあまりなかったと思います.都会では訪問診療専属のクリニックはたくさんあります.僻地では利用者数が多くないため,採算が合わないのです.奥会津は東京23区と同じぐらいの面積ですが,その地域に僕たちが行く前は5人しか常勤医者がいませんでした.
編:その広さを5人の医師でみるのですね.
山中先生:ほとんどは山ですから,人が住める場所は限られてはいますが,5人は少ないですよね. 鎌田先生が入ってくれて,どんどん医師が増えました.病床数は多くありませんが,県立宮下病院があります.そこにもドクターが集まってきてくれました.現在では9名の常勤医がいます.
診療所に赴任すると,住民からの強い要望があり辞めることが困難です.かつては急患対応のため,いつ呼ばれるかわからないので3年間村から出たことがないという医師がいました.これからはチームで医療を支え合うことが大切です.
編 :チームにして訪問診療にすることで医師の生活も変わったのですね.
山中先生:若い医師にたくさん参加していただくため,田舎でもチーム医療をどんどん展開していこうと思います.
編:本日は教授職を定年退職されたあとも,総合診療医として地域医療を支えていらっしゃること,いままで同様に後進の教育にご尽力されていることをお伺いでき刺激を受けました.
総合診療医に関心がある研修医・医学生の読者の方々の参考になれば幸いです.ありがとうございました.