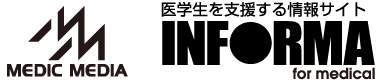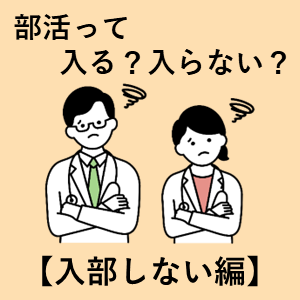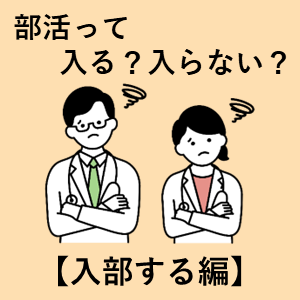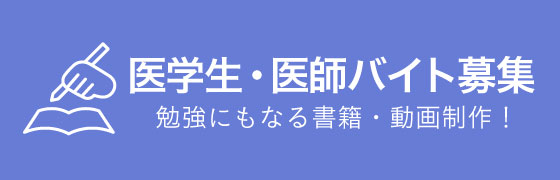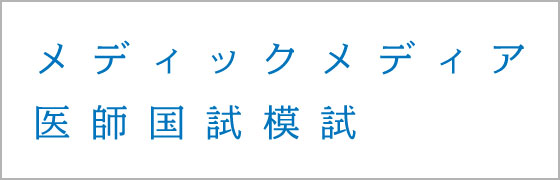[1〜2年生向け]【体験記】医学生の勉強法〜iPad活用術とおすすめ参考書〜
- 現役医学科1年生が試行錯誤の末にたどり着いたiPad活用術を紹介!
- GoodnotesとiPadの機能を使いこなそう!
- 「からだがみえる」もおすすめ!
多くの医学生がiPadを活用して効率的に学習しています.
今回は現役の医学科1年生に実際の勉強方法を取材しました!
まだ勉強スタイルを模索中の医学生や,これから医学生になる方に役立つ内容となっておりますので,ぜひ参考にしてみてください.
試行錯誤の末たどり着いた!効率的な勉強法とは?
T大学 1年生 Mさん
医学部に入って約1年間,色々な勉強法を試しました.
今思い返すとはじめにこの勉強に辿り着いていたら,もっと効率よく勉強できたなと思うので,みなさんの参考になれば幸いです.
目次
- ・ノートアプリはGoodnotes一択
- ①マスキングテープ機能
- ②画像取り込み機能
- ③ペンで擦るだけで消せる機能
- ・iPadの使うべき基本的な機能
- ①Split View
- ②AirDrop
- ③Night Shiftモード
- ・オススメの参考書〜無料で使えるものは使うべし〜
- ①p.338のヘモグロビンの構造
- ②p.540 ネコかん動画 血漿膠質浸透圧
- ③Webコンテンツ(肩の水平屈曲・水平伸展)
- 最後に
————————————————–
・ノートアプリはGoodnotes一択
医学部に合格した後,ひとまずiPadを購入しました.
分厚い医学書を持ち歩くのは大変だし,医学部の先輩たちがiPadで勉強しているのを知っていたからです.
ノートアプリは無料・有料のものがありますが,私はまずはじめにファイルアプリを使っていました.しかし頻繁にエラーが発生し,使わなくなりました.
次にデフォルトでiPadに入っているメモ機能を使いました.これもレジュメに書き込みができたので使えないこともなかったのですが,レジュメ上に画像の貼り付けができないことや,Goodnotesユーザーとの資料の共有に手間がかかるなど不便な事が多く使わなくなってしまいました.
そして最終的にGoodnotes6に辿り着きました.
このアプリはクラスメイトが多く入れていることを知っていたのですが,有料で4,000円以上するので,なかなか手が出せないでいました.
結論,もっと早く使えばよかった!
基本的な使い方は大学で配布されたレジュメをGoodnotesに取り込んで,書き込むという形で使っています.
さまざまな利点がありますが,個人的には以下の3つがめちゃくちゃ使いやすいです.
①マスキングテープ機能
キーワードをマスキングテープ機能で隠して,タップすると消えて下の文字が見えるという機能です.
大学のレジュメにマスキングテープを貼って,知識の確認作業に使っており,テスト前に大活躍しています.
大学受験勉強のときも覚えたい部分を赤シートで隠しながら確認する勉強法をしていたので,同じようなことがiPadでもできて感動しました.
②画像取り込み機能
「からだがみえる(電子版)」や検索で調べたことなどをスクショして,Goodnotesに取り込むことができます.先生のレジュメだけではわからないことをどんどん補足していき,自分なりのノートが出来上がって行くのが楽しいです.
あとは友達のノートまとめが綺麗だったときにその場で写真を撮らせてもらい,1ページ自分のノートに付け足すなんてことも可能です!
③ペンで擦るだけで消せる機能
今まで書いた文字を消すには消しゴムツールに切り替えが必要でした.
しかしGoodnotes6からついたこの機能を使うと,ペンでぐちゃぐちゃっとするだけで書いた文字を消すことができます.
消しゴムを選ぶ必要がないので,感覚的にパッと消すことができて時短になり地味に嬉しい機能です.
・iPadの使うべき基本的な機能
ノートアプリと合わせて,勉強するときは基本的に下記の設定を活用しています.
長時間勉強することが多いからこそ,疲れにくく効率的な設定を自分で見つけられるといいと思います!
①Split View
2 つのアプリを左右に並べて表示できる機能で,使いこなせると格段に勉強効率が上がります.
大学のオンライン授業を左のタブで開いて,右のタブでノートをとるというスタイルで使っています.
▼左側に参考書やレジュメ,右側にGoodnote
②Airdrop
AirDropはiPhoneやiPadなどのAppleのデバイス間で直接ファイルをやり取りできる機能です.特に先輩から資料を貰うときによく使っています.素早く転送できるので時短になりますし,連絡先を知らないクラスメイトにも簡単に共有できるのでよく使っています.
③Night Shiftモード
Night Shiftモードは画面の色味が変えることで目への負担を軽減する機能です.設定から自動で切り替わる時間を設定でき,特に寝る前など薄暗い環境で画面を見る際の眩しさを抑えられます.私は一日中室内で勉強するときは常にNight Shiftをオンにしています.気のせいかもしれませんが,目が疲れにくくなったように感じます.
・オススメの参考書〜無料で使えるものは使うべし!〜
基本的には大学のレジュメ,過去問で手いっぱいになることが多いのですが,メディックメディアの「からだがみえる」はプラスアルファで使っていました.
大学で指定された教科書は文字が多く理解に時間がかかっていたのですが,「からだがみえる」はイラストが多く,とにかく頭に入りやすかったです.
特に医学科1年生は電子版を無料で使えるキャンペーンがあったので,解剖学や生理学の授業でたくさん活用しました.
検索機能があるので,調べたいことをピンポイントで見つけられたのが良かったです.
特にわかりやすかったページを使い方とともに少し紹介させてください!
わかりやすかったページと使い方
①p.338のヘモグロビンの構造
重要な単語にマーカーをひいて覚えるのも良いですが,イラストをなんとなく頭に入れておくだけでも覚えやすくなったり,思い出しやすくなったりします!
大学の授業では文章で一言書いてあるだけということもあるのですが,「からだがみえる」では基本的なことから丁寧に解説してくれるので,高校で生物を選択していなかった私も助かりました.
また知識の定着にはアウトプットが重要です.
「もっとわかる」をタップして出てくる穴埋め問題を活用することで,覚えるべき単語を覚えることができます.選択問題ではCBTの類題も多くあり,低学年で学んでいる内容が数年先の試験にも直結することを意識できることで,自然と覚える意欲を引き出してくれます.
②p.540 ネコかん動画 血漿膠質浸透圧
「からだがみえる」には動画もついています.
実際にこの動画を見て,卵のうえに可愛くデザインされたアルブミンがのっていて,アルブミン=タンパク質というイメージを簡単につけることができました.さらにアルブミンが足りなくなるとどうなるのか,足りなくなる原因は何があるのかまで知ることができ全く知識がない状態で見てもスムーズに知識が入ってくるなぁと感じました.
③Webコンテンツ(肩の水平屈曲・水平伸展)
自分で動かしながら構造を理解できる,Webコンテンツもあります.
大学の外では骨標本に触れたり,人体模型を見たりすることができないため,立体的なイメージを掴むのが難しいことがあります.そんなときに,Webコンテンツの3Dモデルはとても役立ちました.自分で動かしながら様々な角度から確認することで,理解しやすく効率的に学習できます.骨学の試験では本物の骨を見て解答するため,立体的に学習していたことが役立ちました!
最後に
いかがでしたか?
高校までの勉強法を大学でやろうと思っても上手くいかないこともあり,どうすれば効率よく勉強できるか試行錯誤しながら進めている人も多いかもしれません.そんな中で大事なのは,自分なりの学習方法を見つけることだと思います.
大学の先輩の話を聞いたり,SNSで紹介されている勉強法を試したり,情報収集して試して合うものを見つけてくださいね.
また大学でもらったレジュメだけではなく,「からだがみえる」のような参考書を適宜使うことも大事だと思います.自分にとってさらにわかりやすい言い回しで説明されていたり,上で紹介したような動画やWebコンテンツが付いてたりするので,文字を読む以外の方法でも勉強できるのでおすすめです!
ぜひ自分にあった勉強方法を見つけてくださいね!