
mediLink動画
多くの医学生さんに活用いただいている講義動画サービス「Q-Assist」ですが、どのように進めたらよいかわからない、みんながどのような活用をしているのか気になる、動画を効率よく復習する方法はない?といった疑問をお持ちの方も多いかもしれません.
今回は、厚生労働省が公開している国試の出題基準とQ-Assistの講義を組み合わせて,国試直前のピンチから無事合格を掴みとった方の体験記をお届けします。国試が迫ってきて焦りを感じ始めている高学年の方はもちろん,低学年の方の活用法についても満載ですので,ぜひ最後までご覧ください
私の大学では3年生から本格的に臨床科目が始まりました.同時に複数の科目を初学で学ぶ大変さに直面し,3年生の夏ごろにQ-Assist(QA)を購入したのが始まりです.
QAは疾患ごとに動画が分かれており,CBTレベルの動画には「CBTマーク」が付いているので,最初はそのマークのある動画を優先して視聴しました.そのおかげで効率よくインプットでき,無事に3年生の臨床科目の試験は全科目一発合格.4年生の秋にはCBT対策として本格的にQAを活用し始めました.
このとき,テキストには板書の書き込みが既にしてあったため(※編集部注:QAには普通のテキストのほか,あらかじめ講義での板書を書き込んだテキストを配信しています),CBT対策では「先生のコメントや補足」を中心にメモを取り,知識を肉付けしていく感覚で勉強を進めました.またこの段階でCBTマークのない疾患についても一通り視聴し,全体像をしっかり押さえておくことができました.
実習が始まってからもQAは私の強力な味方でした.特に印象に残っているのは「担当疾患を完全に忘れていて、レポートが書けない!」というピンチの時です.そんな時でも,QAは疾患ごとに動画が完結しているため,知りたい疾患だけをサクッと復習することができました.
また,レポートや口頭試問対策としても重宝しました.QAで疾患別に要点を確認してから実習に臨むことで,短時間で必要な情報を整理でき,実習の質も格段に上がったと思います.
さらに実習期間は「暗記から思考へ」と知識を昇華する大事な時期です.QAテキストに「なぜこの症状が出るのか」「治療法は病態とどうつながるのか」などを自分の言葉で書き込み,病態生理から論理的にアプローチするクセをつけるよう意識しました.これが国試直前での暗記量削減にも大きく役立ちました.
ここからが私が一番お伝えしたいポイントです.
実は私は色々と忙しかったこともあって6年生の卒業試験で再試験となり,年明け1月に再試を受けていました.私大に通っている方には共感していただけるかもしれませんが,卒業試験対策と国家試験対策は別物です.私は1月の時点で「国試まで1ヶ月,国試対策はゼロ」という状況でした.
再試後,直近の模試は必修86%,一般臨床72.3%とやや不安な結果でしたが,そこから1ヶ月後の国家試験本番で必修97%,一般臨床85%までスコアを大幅アップさせることができました.その成功の鍵が「戦略的な出題基準対策」でした.
国家試験は厚生労働省が公表する「医師国家試験出題基準」に沿って作問されています.中でも「医学各論」にあるレベル分類(a・b・c)は、実際の出題確率にも直結しており,特にレベルaは70%以上の出題率と言われています(※編集部注:出題基準のレベル分類についての詳細はこちらの記事を参照ください).
私は再試明け,まずQAテキストに全てのレベルa疾患を赤マーカーで囲み,備考欄の重要キーワードにも赤マーカーで下線を引きました.こうすることで「暗記の優先順位」が明確になり,国試直前期に最重要部分だけを効率よく確認できました.
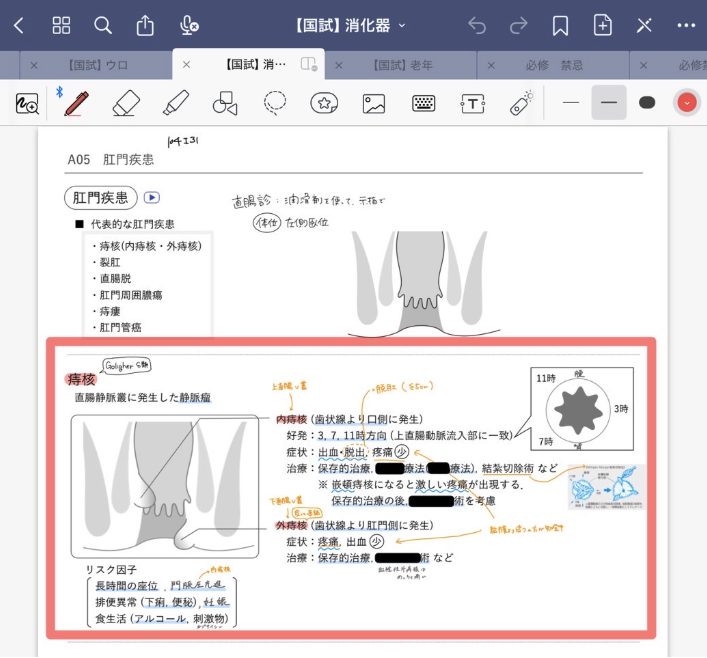
加えて,QAの直前期講座で予想問題や要点整理を行い,自分の理解度を再確認.さらにQB1週目問題で解き間違えた問題だけを重点的に見直すなど,短期間でも最大限に伸ばせる勉強法を実践しました.
その結果,119回国試の初日Aブロックでは「この問題も出題基準aだ!」と冷静に対応でき,周囲が動揺する中でも平常心を保つことができました.診断がつかない問題でも,選択肢に疾患が列挙されている問題で,5つの選択肢のうち4つが「出題基準a」であり、4つとも確実に該当しないと確信することで正解に辿り着けた場面もありました.
QAを最後まで使い続けてよかったと感じたのは「動画1本が疾患単位」で完結していることです。他社の動画だと1本1時間超のボリュームで,どこに見たい疾患があるのか探すのに時間がかかることも.しかしQAなら「今この疾患だけを復習したい」という時に,迷わずピンポイントで学習できます.実習中も国試直前も,このコンパクトさに何度助けられたかわかりません.
皆さんも普段の定期試験では「先生が大事と言ったところ」を重点的に確認しますよね.国家試験も同じです.厚生労働省が「大事」と明言している出題基準を意識して学習することが,合格への近道になるはずです.
3・4年生でQAを使い始めた皆さん,ぜひ5・6年生でも使い続けてみてください.実習でも国試直前でも,きっと「QAで良かった」と思える瞬間がたくさん訪れると思います.
厳しい道のりかもしれませんが,戦略的に勉強すれば必ず突破できます.応援しています!