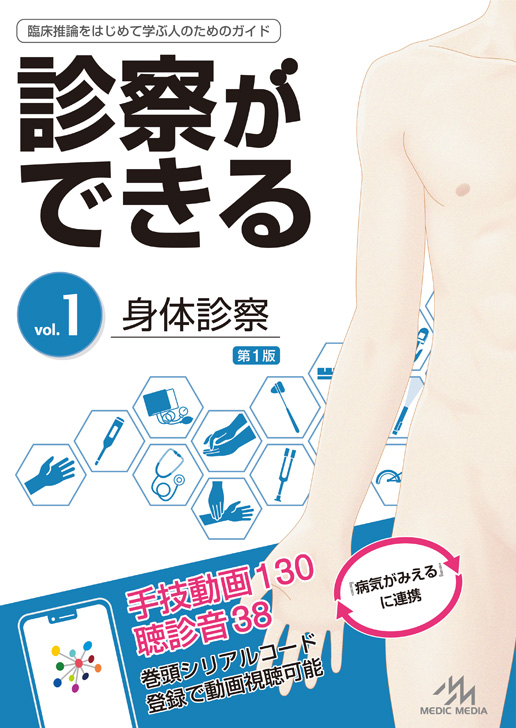
診察ができる vol.1 身体診察
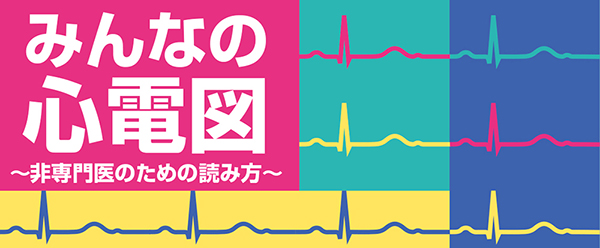
———————————–
バックナンバーはこちら
———————————–
心電図の解釈を始める前にまずは電極のつけ方を覚えなければなりません.
目の前に胸を抑えて苦しむ人がいる場面で,
さっと心電図を付けられるというのは全ての医療者にとって大切なことです.
心電図には基本的な誘導法が12種類あります.
“誘導”とは小難しい言葉ですが,
心臓を“どこから見ているか”と考えてください.
12誘導に対して,体につける電極は10個あります.
12誘導は記録用紙の
左側に示される肢誘導(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,aVL,aVF,aVR)と,
右側に示される胸部誘導(V1-V6)に分かれます.
肢誘導をみるのは両手両足の電極です(うち1つはアースです) .
胸部誘導は胸骨をメルクマール(目印)につけます.
前胸部でポコッと飛び出す部分(解剖学的には胸骨角と呼ばれる部分)を探します.
そこが第2肋骨のくっついているところです.
指をなぞるように下へと動かし,
胸骨右縁第4肋間にV1を付けます.
対側の胸骨左縁第4肋間にV2を付けます.
次は,V3を飛ばしてV4です.
V2の1つ下の第5肋間をなぞるように左下へと指を動かし,
ちょうど鎖骨中線のところでV4をつけます.
そして,V2とV4を結んだ線の中点にV3を付けます.
V6のつけ方がよく間違えやすいので,ポイントです.
時にV2とV4を結んだ線の延長とこの中腋窩線とが交わる
ずいぶんと低いところにつける方がいるのですがそれは誤り.
V6はV4と同じ高さの中腋窩線につけるきまりになっています.
V5は前腋窩線上のV4と同じ高さにつけます(前腋窩線に相当).
ショックバイタルや急変時など,救命医の怒号が飛び交う慌ただしい状況でも,
冷静に解剖を確認してすばやくつけることができれば一人前です.
電極には必ず色がついています.これは間違えないように全国共通です.
当然電極位置を間違えると12誘導は逆転した波形が出て
解釈トラブルが起きるので注意をしましょう.
なお,心電図検定を含めて,心電図クイズ本には
左右の肢誘導電極のつけ間違えが有名なテーマとしてしばしば出題されています.
ちまたでは胸部誘導の順番を
「あきみちゃんのブラは紫」
すなわち
「あ(赤:V1)き(黄:V2)み(緑:V3)ちゃん(茶:V4)の
ブラ(ブラック〔黒〕:V5)は紫(V6)」
とゴロで覚えるそうです.
(これを覚えても良質な知識にもならないのですが,
慣れずに付け間違えるよりはマシです.)
次に,波形の名前を覚えましょう.
心電図の基本波形は,P波,QRS波,T波と
名づけられています(U波がみられる場合もある).
名づけたのは,心電図の発明者である
アイントーベン(Einthoven)ですが,
彼はなぜ,”A”波ではなく”P”波から始まると定義したのでしょうか?
実は誰もがその答えを知りません.
地震もP波(縦波)から始まり,次いでS波(横波)が来ますが,
この“P”はPrimary waveの略だそうですが,これと同じというのが有力な説です.
後に心電図のP波は心房の収縮を示すことが知られるようになりました.
Pに続く波をさらに,アイントーベンはQRS波,T波とよびました.
QRS波は基礎疾患や誘導によって様々な形を呈します.
この時の呼び方のルールを知らないと
心電図関連書籍を読むにあたって困ってしまうので紹介します.
例えば「rSR’パターン」などという呼び方を耳にしたことはありませんか?
これは右脚ブロックの際にV1-V2付近でみられる波形です
一見複雑な,こうしたQRS波の命名法は
実は以下のシンプルなルールで定義されています.
〈1〉初めに出現する下向きの波形はQ波とよぶ
〈2〉初めに出現する上向きの波形はR波とよぶ
〈3〉2回目に出現する下向きの波形はS波とよぶ
〈4〉2回目に出現する上向きの波形はR’とダッシュをつける
〈5〉波が大きければ大文字,小さければ小文字で記す
※例外として下向きに深い波が1個だけあるような時には「QSパターン」とよぶ
今回のまとめ
●10個の電極の付け方を覚える.
●心電図の基本波形は,P波,QRS波,T波.
![]() 著者:Dr. ヤッシー
著者:Dr. ヤッシー
内科医.心電図読影へのあくなき探求心をもち,
循環器非専門医でありながら心電図検定1級を取得.
これまでに得た知識・スキルを臨床現場で役立てることはもちろん,
教育・指導にも熱心.若手医師だけでなく,
多職種から勉強会開催の要望を受けるなど,頼られる存在.
→【第6回】P波はⅡ誘導とV1誘導を見よ (刺激伝導系その1 心房の伝導)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
主要疾患が大改訂!Webコンテンツがパワーアップ!
『病気がみえる vol.2 循環器 第5版』発売中
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
–「みんなの心電図」目次–
【第1回】連載のコンセプトと自己紹介
【第2回】初学者はなぜ,心電図を苦手と感じているのか?
【第3回】心電図でわかること,わからないこと
【第4回】近づく電気,離れる電気
【第5回】電極のつけ方と基本波形
【第6回】P波はⅡ誘導とV1誘導を見よ (刺激伝導系その1 心房の伝導)
【第7回】心房から心室へは1本道(刺激伝導系その2 房室結節の伝導)
【第8回】心室壁の高速道路と一般道 (刺激伝導系その3 ヒス-プルキンエ線維の伝導)
【第9回】心室壁はつっかえないように縮んで,伸びる(QRST波形理解の下準備その1)
【第10回】パッチクランプ法でみる細胞1粒の活動電位(QRST波形理解の下準備 その2)
【第11回】QRST波形の成り立ち(刺激伝導系その4 心室の興奮と弛緩)
【第12回】QRS波の胸部誘導でのグラデーションを感じよう
【第13回】心電図を確認する眼の動き
【第14回】冠症候群の診断は合わせ技1本
【第15回】心筋梗塞の心電図の成り立ち (1)T波増高
【第16回】心筋梗塞の心電図の成り立ち (2)ST上昇
【第17回】心筋梗塞の心電図の成り立ち (3)異常Q波
【第18回】心筋梗塞の心電図の成り立ち (4)冠性T波
【第19回】心筋梗塞の心電図は出る順番が大切
【第20回】心内膜下虚血の心電図 ST低下
【第21回】ST変化の鏡面像(Mirror image)
【第22回】冠血流域と誘導の対応関係
【第23回】速読式 心拍推定
【第24回】速読式 QT延長推定と基礎疾患
【第25回】頻脈の読影が心電図では最も難しい
【第26回】頻脈性不整脈の分類 (1)上室性と心室性
【第27回】頻脈性不整脈の分類 (2)上室性頻脈の種類
——————————————————–
本連載の続き・バックナンバーはこちら
——————————————————–